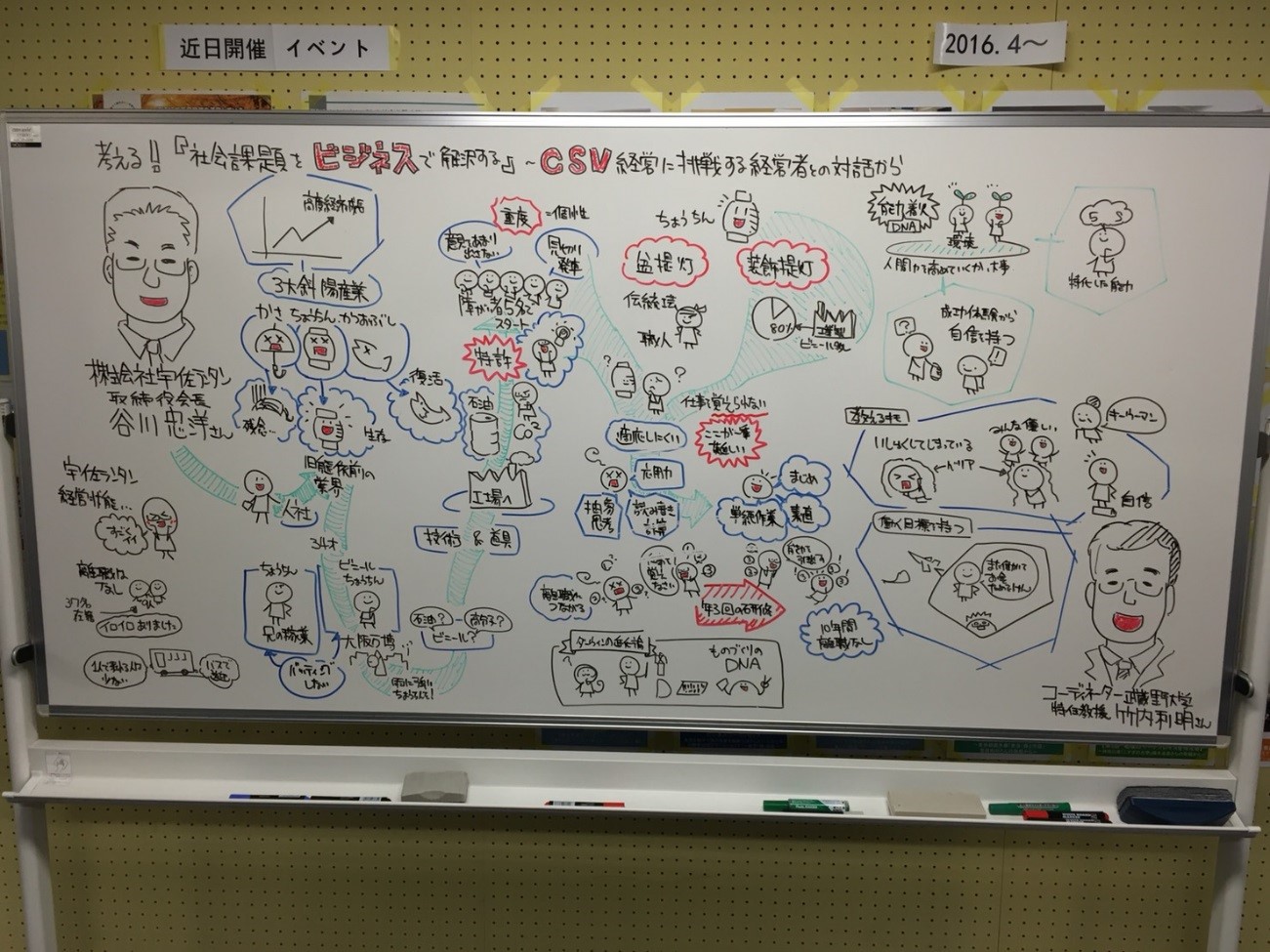■障がい者雇用は難しい?
障がい者を社員として雇用することは簡単なことではない。厚生労働省が2016年に実施した調査では、障がい者の法定雇用率2.0%を達成している民間企業は48.8%であり、約半数の企業が障がい者雇用を採用している。しかし、障がい者を雇用している企業でも、義務的に、彼らを「お客様」として扱う企業も少なくないという。その原因のひとつは、障がい者を雇用することのデメリットにしか目が行っていないことにある。確かに、知的障がいを持つ人たちは読み書き、計算、数量の把握等が不得意であるため、マニュアルを渡して「この通りやってほしい」と言われても難しい。さらに、彼らは応用が難しいため、作業工程が複数にわたると戸惑ってしまう。したがって、常に誰かのケアが必要となるため、その分他の従業員の労力が削れてしまい、全体の生産性が下がるという論理は間違っていないかのようだ。しかし、彼らの得意分野に目を向けると、健常者とは違った彼らならではの雇用方法が見えてくるだろう。今回のゲストである谷川忠洋氏いわく、知的障がいを持つ人たちは、単純作業に強く、1度覚えた仕事は着実に長時間続けることができる。したがって、ひたすら1つの作業に注力できる業務であれば、彼らの才能をいかんなく発揮できる。
谷川氏が会長を務める株式会社宇佐ランタンの社員数は14名であり、その内の9名が知的障がい者だ。宇佐ランタンの主力商品は日本の伝統工芸品である提灯であり、通常は職人が1人で全ての工程を手掛ける。しかし、同社ではその工程を3つに分け、知的障がいを持つ人たちの能力を最大限に引き出している。「普通の人なら辟易するような単純な作業をずっと、熱心にやってくれる」(谷川氏)。現在の宇佐ランタンのオペレーションは、30年以上彼らと寄り添い、試行錯誤してきた谷川氏が見出したものだ。また、同社は障がい者を雇用するうえで、多くの経営者が懸念するであろう生産性の問題もクリアしている。同社の過去2年の対前年比売上高は104%、107%と、堅調に推移してきている。これは、障がい者を雇用することで生産性が下がるという意見に対するアンチテーゼとなる。
障がい者雇用は、単なる社会課題の解決ということだけではなく、確かにメリットが存在する。しかし、そのメリットを生み出すためには、その特性を活かす仕組みを作らなければならない。谷川氏も初めから障がい者のことを理解し、彼らの特徴を活かすような仕組みを用意していたわけではなく、長い年月をかけて多くの困難を乗り越えてきた結果が、今の宇佐ランタンの姿だ。
■障がい者とともに育つ
谷川氏は大分県で5人兄弟の末っ子として生まれた。楽器屋でアルバイトをしながら大学に通っていた同氏の人生に転機が訪れたのは昭和39年、東京オリンピックの年だった。兄に連れられ提灯屋に丁稚として働き始めた同氏は、古いしきたりやしがらみの中で生きている提灯屋の経営に疑問を持つようになった。その後、父親の病気を機に故郷である大分県に帰った谷川氏は1973年に「株式会社宇佐ランタン」を立ち上げた。同氏は、丁稚時代に客先で聞いた「雨に強い提灯はないのか」という言葉が耳に残り、また自身の大学での専攻が水産化学であったこともあり、ビニールで提灯を作ることを決意した。当時の提灯は全て紙製であり、水に弱く、1度濡れてしまうと使い物にならなくなってしまっていた。その中で、ビニールという水に強く、さらに安価で生産できる提灯の需要は高く、宇佐ランタンの滑り出しは上々だった。
宇佐ランタンが障がい者雇用を始めたのは、1981年だ。自立訓練に携わる知人の声かけで、5名の雇用を開始した。谷川氏は障がい者雇用を始めた理由について「よく聞かれるが自分でもわからない。しかし、苦学生時代のことを思い出し、焼けぼっくりに火が付いたのだと思う」(谷川氏)と語る。使命感のようなものに突き動かされて始めた障がい者の雇用は、同氏曰く「見切り発車」だった。
今よりも障がい者に対する理解も知識も乏しい時代に、彼らを従業員として雇うことの難しさは想像に難くない。「30年間で37名の障がい者が在籍していたが、今働いているのは9名。彼らの特性を理解しておらず、自分の指導方法が間違っていた。業務を教えようとすればするほど、彼らを委縮させてしまった」と語る谷川氏の顔は後悔してもしきれないといったような悲哀の色が伺えた。
多くの失敗を重ねてきた30年間で、谷川氏は障がい者に対する理解を深め、彼らに最適と思われる業務オペレーションを編み出したが、同氏が最も重視したことは障がい者の心のバリアを取り払うことだ。障がいを持つ人は、疎外され、人を信じられなくなっている人が多い。その障壁を取り除かなければ、どれほど彼らを理解し、仕組みを作っても機能することはないという。宇佐ランタンでは、障がい者の個々のバリアを取り払い、業務に従事できるようにするために大きく2つの取り組みを実施している。1つ目に、年3回の実習だ。障がい者は「出来ない」のではなく、「出来るまで時間がかかる」というのが谷川氏の持論だ。そのため同社では、障がい者に対し入社前に1年間、①社内の環境に慣れ、1日の仕事の流れを把握する②本格的に仕事にかかる③技術、自主性を高める訓練(それぞれ期間は1、2か月)という3つのフェーズに分け実習を行っている。3回目の時点で、業務は健常者の50%に達することが目標だ。覚えることが苦手な知的障がい者に対し、覚えることを少なくして能力を引き出そうという谷川氏の考えに基づくものだ。宇佐ランタンが実施している工夫の2つ目は会社に保育器としての効果を持たせることだ。社内を安全で信頼できる保育器のような環境にすることで、障がい者のポテンシャルを引き出そうと考えている。この保育器効果を取り入れるためのキーパーソンは、社内で「かあちゃん」と呼ばれ、創業当時から障がいを持つ従業員を見守ってきた女性だ。何かあれば「かあちゃん」がすぐに相談に乗ってくれるという環境は、障がい者にとって安心につながる。
障がいを持つ人のことを理解し、彼らのための環境を整えてきたことを谷川氏は彼らに「鍛えられた」と表現している。「はじめは『管理』しようと思っていて、失敗した。(彼らの力を)『引き出す』やり方に変えることで、ようやく彼らと働けるようになった。障がい者雇用を始めて30年間、彼らに鍛えられながら互いに成長することができた」(谷川氏)。長い年月を障がい者と共に過ごし、彼らのポテンシャルを信じ続けてきた同氏だからこそ、障がい者が働きやすい環境を作りながら、健全な経営状態を維持するという至極難しい舵取りを実現できたのだろう。
■非日常、此処に在り
谷川氏の講演終了後、学びをシェアする時間が設けられた。筆者が参加したテーブルには、福祉に携わる参加者が多く、皆自身の業務と講演の内容を照らし合わせ語っていた。意見を抜粋して紹介する。
「障がい者にルーティーンを定着させるために教育をしていたが、谷川氏の話を聞いて、教育以外の手法もあるのかもと感じた。具体的な方法はまだ思いつかないが実践していきたい」(学習支援NPO法人)
「役割の振り方もそうだが、何より環境づくりが大事だと学んだ。障がいを持つ人に振る業務を何にするかはそう難しくはなさそうだが、彼らが働きやすい環境を作るには時間も手間もかかるだろう」(自営業)
「障がい者とのかかわりの中で健常者も変わっていくことは日常の業務の中でも感じていた。お互いが刺激になれるような仕組みづくりに励んでいきたい」(障がい者雇用支援)
グループの中でも多くの意見が出たが、ふと周りを見渡すと、どのグループも同じ程度の熱気で議論を交わしていた。感じたこと、谷川氏に聞いてみたいこと、それぞれのテーブルで思い思いの話が飛び交う様子に、司会も「終了のベル」を鳴らすタイミングを計りかねていた。
既に社会課題に向き合っている人、これから向き合っていこうとしている人、様々な人が集まっていた。その誰しもに共通していたことは、かなり真剣だということだ。社会課題について、なんとなく「解決しなければいけない」と考えている人は多いだろう。しかし、ほとんどの人は実際に行動に移すことはない。さらに、自分がこれから起こそうとしているアクションについて誰かに熱く語りたいと思っても、「やろうとしていることはすごいけど、自分には関係がない」と、まともに取り合ってもらえないこともある。TIP*Sという場では、皆が真剣に意見を述べ、フィードバックをもらい、本気で取り組んでいきたいという意気込みがさらに周囲に伝播していく。宇佐ランタンが子供を保護し育てる保育器だとすれば、TIP*Sには純粋な心を持った子供たちを温かく見守り、その熱意をさらに育てていく空気があるようだ。